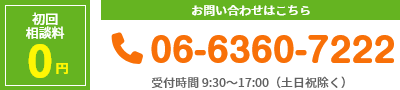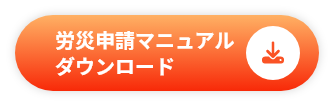いわゆる「労災かくし」とは
仕事中や通勤途中で怪我や病気になった場合、まず最初に、ご自身や家族の方が、会社に対して「労災保険を使用できるか」、「労災保険によって治療費や休業補償などを支払ってもらえるか」について確認されるかと思います。
それに対して、会社から以下のような説明、対応を受けた場合は、会社が「労災かくし」をしている可能性があります。
「労災保険は使わせない!」と言われる場合
労働災害が発生した場合、会社は「労働者死傷病報告」(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)の提出を義務付けられていますが、会社が意図的に、その提出を怠っている場合です。
これは明らかな「労災かくし」であり、労働災害に遭われた方も、「おかしいのでは??」と気付きやすいかと思います。
次のような説明がある場合
「うちの会社は労災保険に入ってない」
一般的に労災保険に加入していないということはありません(加入していない場合は追徴金徴収や費用徴収といったペナルティがあります)。仮に労災保険に加入していなかったとしても、労災申請することはできます。
「アルバイトだから労災保険が使えない」
アルバイトやパートの方でも労災保険は適用されます。
「治療費は会社が負担するから、健康保険を使って病院に行ってくれ」
労災を使えば、治療費(療養給付)だけでなく、休業補償給付や後遺障害が残った場合の給付もされます。
このような説明の場合は、労働災害に遭われた方としては、会社の説明に納得してしまったり、「治療費を負担してもらえるなら、まぁいいか」と考えてしまう可能性があります。
しかし、会社としては、様々な理由から労災を使わせない方向へ持って行こうとしている可能性があります。
事業主証明を行ってくれない場合
さらに申請の際に必要となる各種給付請求書には、会社の名称や所在地、事業主の氏名を記入する欄(事業主証明欄)があります。
しかし、この事業主証明を行ってくれない場合もあります。
会社側としては、目撃者がいないなどの事情から、労働災害の発生を確認できないため、事業主証明をしたがらない場合があります。
しかし、会社が事業主証明をしてくれない場合も、労災申請はできます。
会社が労災を使用したがらない理由
主な理由としては、次のようなものが考えられます。
1 実際に労災保険に入っておらず、労災申請をされるとそのことが発覚してしまう
2 会社としても、従業員に対する安全配慮が足りていないことを自覚しており、労災申請をされ、労基署からの調査が入ると様々な問題が発覚するおそれがある
3 取引先・今後の営業活動に対する配慮をしている
4 労災保険を使うと、保険料が上がるのではないかという心配(この点に関しては必ずしも保険料が上がるものではありません。メリット制(労働保険徴収法第12条第3項)参照)
5 労災申請に関する手続きに時間を取られたくない
いずれの理由も会社都合であり、労災に遭われた方やその他の従業員のことを考えての事ではありません。
労災事故により怪我をされた場合は、治療費や生活費、また将来のことなど心配は尽きないのですから、会社の都合に関わらず、労災保険を申請されるべきです。
会社が労災隠しをする場合、非協力的な場合の対応方法
労災申請は可能です
・会社が労災保険の使用を認めない場合
・会社が労災保険の使用に協力してくれない場合
・会社が事業主証明を行ってくれない場合
・会社が本当に労災保険に加入していない場合
いずれの場合でも、労働災害に遭われた方は、労災申請し労災保険を受け取ることは可能です。
そして、労災申請をして労災保険を受け取られることが、その後の損害賠償請求による十分な損害の補償につながります。
会社が上記のような対応をとってきたとしても、決して諦めずに労災申請に向けて行動してください。
具体的な対応方法
① 労働基準監督署に会社の対応を報告し、今後の手続について教えてもらう。
会社が労災隠しや非協力的な対応をしていることを労基署に伝えることで、労基署が事実関係を確認したり、場合によっては会社に指導をしてくれる場合があります。
それにより、会社が労災使用に協力的になることもあります。
また、労基署は会社が協力してくれない場合の労災保険の申請方法を具体的に教えてくれることでしょう。
② 弁護士へのご相談もご検討ください。
弁護士に早期にご相談いただくことで、労基署と同様に労災申請の方法をアドバイスすることができます。
それだけでなく、労災では補償されない慰謝料や休業損害の一部、逸失利益などの損害賠償請求に向けた準備を早い段階から進めることができます。
損害賠償請求のためには、「会社側にも責任を問えるのか?」、「事故当時の状況は?」、「後遺障害が残る場合どうしたらいいのか?」、「請求できる損害額は?」、「そのためにはどのような証拠を集めたらいいのか?」など様々な問題をクリアしていく必要があります。
弁護士にご依頼いただくことで、過去の裁判例や文献を調査し、これまでの経験を踏まえて、会社側に責任の有無や損害内容について、より正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能となります。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士は被害に遭われた方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労働災害に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。