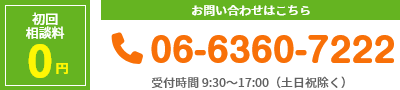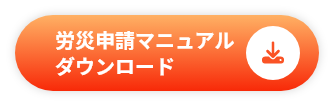介護現場での利用者からの暴力など
介護施設、訪問介護などの介護現場において、介護従事者が利用者又はその家族から身体的暴力、精神的暴力、セクシャルハラスメントなどのいわゆるハラスメントを受けることがあります。
身体的暴力の例
殴られる、蹴られる、物を投げつけられる、首を絞められる、手をひっかく、唾を吐きかけられる など
精神的暴力の例
大声を発する、どなる、威圧的な態度で文句を言い続ける など
セクシャルハラスメントの例
必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、女性のヌード写真を見せる、卑猥な言動を繰り返す など
このような身体的・精神的暴力などを受けたとしても、「利用者が病気、精神障害だから仕方がない」とか、「介護従事者としてうまく対応ができなかったから」などと考えがちであり、結果として、介護従事者も会社側も問題として認識しないまま、介護従事者が我慢するというケースも多くあります。
利用者から身体的・精神的暴力など受けた場合どうすればよいか
利用者が身体的・精神的暴力などに及ぶ原因は、利用者の生活歴や病気の影響、コミュニケーション不足など様々あると思われますが、まずは会社に相談し、ハラスメントの問題を共有することが大切ですので、一人で抱え込まずに会社に相談することをおすすめします。
また、利用者から身体的・精神的暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合は、メモや録音などで記録し、相談したときの会社の対応も記録しておくことをおすすめします。
ケガをしたり、精神的に辛い状況が続くという場合は無理をせず、医師の診察を受けて診断書をもらいましょう。
労災請求ができるか
介護従事者が、就業中に、利用者から身体的・精神的暴力、セクシャルハラスメントを受け、それによりケガを負ったり、うつ病などの精神障害を発症した場合は労災に該当する可能性があります。
労災の申請をして労災認定されれば、療養補償給付、休業した場合の休業補償給付、後遺障害が残った場合の障害補償給付などの補償を受けることができます。
(なお、精神障害の労災認定については、「うつ病など精神疾患の方へ」のページにて詳しく記載しておりますので、そちらをご覧ください。)
労災保険からの補償が不十分な場合はどうするか
労災保険からの補償が受けられても休業補償や慰謝料の点で十分な補償が受けられないという場合があります。
また、仮に後遺障害が残った場合、本来なら、将来働いて得ることができたであろう利益(逸失利益)の補償も十分ではありません。
補償が不十分な部分については、身体的・精神的暴力などをした本人に対して損害賠償請求をするのが原則ですが、介護施設等の利用者である場合は認知症や精神障害の影響で責任能力がなく請求できないということもあります。
では、会社に対して損害賠償請求をすることはできるでしょうか。
雇用主は、労働契約に基づき、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする、安全配慮義務を負っています(労働契約法第5条)。
したがって、介護施設等においては、従業員が利用者から暴力などを受け、ケガなどの傷病を負う予見可能性があるにもかかわらず、暴力行為に対して直ちに複数人で対応できる体制を整えるなどの予防策を講じていなかった場合には、雇用主である会社に安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求ができる可能性があります。
早めのご相談、ご依頼で安心を
労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
弁護士にご依頼いただくことで、過去の裁判例や文献を調査し、これまでの経験を踏まえて、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労働災害に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。