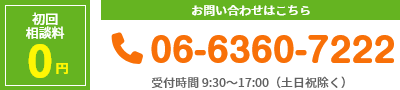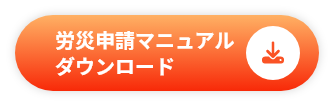労働災害(労災)に遭われた被災者の方は、労災保険から休業(補償)等給付を受けることができます。
この記事では、休業(補償)等給付について詳しく説明いたします。
休業補償等給付とは
仕事または通勤が原因でケガをしたり、病気にかかってしまい、その治療のために会社を休んでおり、給料を受け取っていない場合に支給される労災給付です。
給付を受けられる人
次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。
①業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
②労働することができないこと
③賃金を受けていないこと
有給休暇を使う場合は③を満たさないことになり、休業補償等給付を受けられません。
休業補償等給付の内容とポイント
休業補償等給付の支給額
1日当たり給付基礎日額の80%が支給されます。
・休業補償給付が給付基礎日額の60%
・特別支給金が給付基礎日額の20%
これらの合計である80%が支給されるだけで、賃金の100%が補償されるわけではありません。
給付基礎日額の計算方法
給付基礎日額は次の方法で計算されます。
原因となった事故直前3か月の賃金合計÷暦日数
※賃金合計に、臨時で支払われる賃金、賞与、ボーナスなどは含みません。
これを具体例で計算してみます。
A社から毎月200,000円の賃金を得ていたところ、10月に労災発生した場合
7月分賃金:200,000円+8月分賃金:200,000円+9月分賃金:200,000円=600,000円
暦日数は、7月が31日、8月が31日、9月が30日、合計92日
↓
600,000円÷92日≒6,522円が給付基礎日額となります。
いつから給付されるか
休業補償給付は、休業4日目から給付されます。
休業1日目から3日目は「待機期間」といい、労災から給付を受けることができません。
但し、業務災害の場合は、雇用主から平均賃金の60%の給付を受けられます。(労働基準法76条)
いつまで給付を受けられるか
基本的には労働者が再度働けるようになるまでは給付を受けることができますが、症状固定して治療が終了すると、復職していなくても休業補償は打ち切られます。
症状固定後に後遺障害が残った場合は、労働基準監督署に申請して後遺障害の認定を受けます。
後遺障害の認定を受けると、症状固定の時から、障害の程度に応じた障害補償給付を受けることができます。
また、療養開始後1年6ヶ月経過し、そのケガ又は病気が症状固定(治ゆ)しておらず、傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)等年金に移行します。
休業補償給付の申請方法
休業補償の申請書を所轄の労働基準監督署長に提出します
休業補償の申請について、会社経由で申請するのが一般的のようですが、労働者が自ら申請することも可能です。
申請書の様式
業務上の災害の場合と、通勤災害の場合とで申請書が異なります。
・業務災害…休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式8号)
・通勤災害…休業給付支給請求書(様式16号の6)
申請書は、厚生労働省HPの「休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続」のページからダウンロードができます。
「休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続」パンフレット(厚労省)>>>
申請書一覧はこちら「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」(厚労省)>>>
申請に必要なもの
医師の証明
労災による療養のため働けない状態であることを医師に証明してもらう必要があります。
申請書を病院へ持参し、医師に記入してもらいます。
会社の証明
申請書に会社の記入欄があります。
申請書を提出してから実際に受給できるまでの期間
申請から実際に受給できるまでは約1か月程度ですが、1か月以上かかる場合もあります。
また、休業が長期にわたる場合は1か月ごとに請求するのが一般的です。
休業補償給付の消滅時効は2年
休業補償給付を受ける権利は、休業期間中の賃金支払日ごとに発生し、その翌日から2年を経過すると時効により権利は消滅します。
時効による請求権の消滅にはご注意ください。
【注意点】治療のため会社を休んだ期間の賃料全額が補償されるわけではない
休業補償は休業4日目以降から給付されますので、休業3日目までは労災からの補償はありません。
また、給付額は1日の給付基礎日額の80%であり、賃金全てではありません(休業補償給付については60%)。
会社を休んだ期間の賃金の全額が労災で補償されるわけではないという点に注意が必要です。
労災による補償が十分ではないかもという場合
労災事故について会社に法的責任がある事案では、労働者の過失割合を考慮しても労災による補償だけでは不十分という場合もあります。
特に後遺障害が残るような重大なケガや疾病の場合は労災による補償だけでは十分ではないことが多いかと思います。
そこで会社に対して損害賠償請求することができるかを検討することになります。
会社の法的責任の有無や過失割合の判断は難しい問題です。
ましてや、大きなお怪我をされ、治療をされている労働者の方が、会社との交渉に向けて準備をすることは精神的にもかなりの負担になるかと存じます。
今後、会社へ請求することも検討される場合には、出来るだけ早い段階で、弁護士に相談をされて、今後の流れ等の確認をされることをおすすめします。
労働災害に遭われてお悩みの方は、一度ご相談ください。