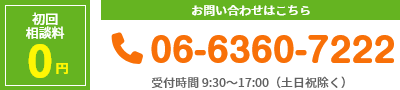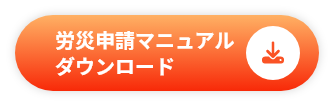はじめに
荷物の積み下ろし作業中、または配達中にケガをしてしまったことはありませんか?
仕事中のケガは「労働災害」にあたり、労災保険の対象となります。
「自分がミスしたのだから…」、「これくらいの怪我で…」と我慢せずに、まずは会社に報告し、労災保険の申請を行いましょう。
もしかしたら、会社は従業員に対して十分な安全配慮をしていなかったので、あなたがミスをしてしまい、労災事故が発生したのかもしれません。
会社側に安全配慮義務違反などが見られる場合は、損害賠償請求も可能です。
運送業界は、全業種の中でも労災発生件数が2番目に多く、毎年、15,000件を超える事故が発生しています(統計上、令和5年は16,215件、令和4年は16,580件)。
さらに、運送業における労災による死亡事故は、増減を繰り返しながらも、全体として増加傾向にあります。
高齢労働者の労働災害発生率が高いことも、運送業における特徴といえます。
事故が起こりやすい作業内容としては、特に、荷物の搬出入時に発生する事故が多く、重傷を負ってしまうケースも少なくありません。
今回は、運送業における労災事故の中でも、荷物の搬出入時に起こりやすい事故の類型について詳しく解説していきます。
荷役作業における5大災害
トラック・荷台からの墜落・転落
トラックの荷台は高所に位置し、荷物の積み降ろしの際にバランスを崩したり、荷物に気を取られて足元や進行方向への注意が散漫となり、つまずいたりして転落する事故が多発しています。
また、不安定な荷の上での荷締め、ラッピング、ラベル貼り等の作業に墜落・転落事故が発生しがちです。
特に、雨天時や暗所での作業は注意が必要です。
荷崩れによる事故
積み上げられた荷物が崩れることで作業員が下敷きになる事故が発生します。特に重量物や不安定な積載物は危険であり、適切な固定措置が必要ですし、ロープ掛け作業中、ロープ解き作業中も荷崩れによる事故が多発しています。
フォークリフト使用時の事故
フォークリフトの操作ミスや死角による衝突事故が発生しやすい状況です。急発進、急停止、急旋回による事故、後方確認不足や過積載による転倒が問題となっています。
トラックの逸走、無人暴走
エンジンをかけたまま停止中、サイドブレーキの引き忘れ等により、停車中のトラックが誤って動き出すことで作業員が巻き込まれる事故が起こります。車両の確実な駐車操作や輪止めの徹底が重要です。
トラック後退時の事故
後退時に周囲の作業員が巻き込まれるケースも多く報告されています。後方確認の徹底や、誘導員の適切な立ち位置、運転手と誘導員との適切なコミュニケーションが必要となります。
労災保険について
労災保険は、業務中の事故やケガに対して適用される公的な保険制度で、労働者が一定の補償を受けられるようになっています。
会社の規模や雇用形態に関係なく、正社員はもちろん、パートやアルバイトなどの非正規雇用の労働者にも適用されます。
主な補償内容は以下の通りです。
• 療養補償給付(治療費の全額補償。病院の自己負担は不要)
• 休業補償給付(労災による休業期間中の給与の約80%が支給される)
• 障害補償給付(後遺障害が残った場合、その程度に応じた補償金が支給される)
• 介護補償給付(後遺障害で介護が必要になった場合の補償)
• 遺族補償給付(死亡時に遺族へ補償金が支給される)
• 葬祭料(労災事故で亡くなった場合、葬儀費用が支給される)
労災事故に遭われた直後は、当面の治療費や生活費の確保の問題がおありかと思います。
また、治療を続けてもケガが完治しないときは、後遺障害と認定されるのか、今後の生活はどうなるのかご不安がおありかと思います。
これらの点については、まずは労災保険に申請をして、保険金の支給を受けられるべきです。
もし、会社の協力が得られなくても、申請は出来ますので、ぜひ、申請されることをお勧めします。
会社に損害賠償請求をするという選択肢
労災保険からの給付には慰謝料がなく、休業補償給付も100%ではありません。また、仮に後遺障害が残った場合、本来なら将来働いて得ることができたであろう利益(逸失利益)の補償も労災保険だけでは十分ではありません。
そのため、十分な補償を受けるために、労災保険の申請だけでなく、他の従業員や会社に対する損害賠償請求を検討することになります。
もし、加害者がいる場合には、その加害者本人だけでなく、会社に対しても使用者責任(民法715条)を追及し、損害賠償請求ができます。
また、加害者がいない場合(すなわち、自分のミスによる事故の場合)でも、会社に損害賠償請求が出来ることがあります。
会社には「安全配慮義務」、つまり労働者が安全に働ける環境を提供する責任があり、「安全配慮義務違反」が認められる場合には、会社に損害賠償請求ができます。
「安全配慮義務」は、業種、作業内容、作業環境、被害者の地位や経験、当時の技術水準など様々な要素を総合的に考慮してその内容が決まります。
「会社に安全配慮義務が認められる場合」とは
では、「会社に安全配慮義務が認められる場合」とはどのような場合か、これから詳しく説明いたします。
トラック・荷台からの墜落・転落事故の場合
• 作業場に手すりや転落防止措置がなかった場合
• 高所作業に関する適切な指導や安全教育が行われていなかった場合
荷崩れによる事故の場合
• 荷物の固定が不十分であったにも関わらず作業をさせられている場合
• 適切な積載管理が行われず、過積載が原因で事故が発生した場合
フォークリフト使用時の事故の場合
• 会社がフォークリフトの点検を怠り、故障した車両での作業を命じた場合
• 作業員にフォークリフトの操作資格がないにも関わらず、運転をさせられている場合
トラックの無人暴走事故の場合
• 駐車時にサイドブレーキをかける、場所によっては輪止めをするような基本的な安全指導がなかった場合
• 会社がトラックの整備・点検を怠っており、ブレーキの不具合が原因で事故が発生した場合
トラック後退時の事故の場合
• 誘導員の配置が必要であったにも関わらず、適切な安全対策が取られていなかった場合
• 後方確認のためのカメラやセンサーが故障していたにも関わらず、修理されずに使用された場合
このように、会社が適切な安全対策を怠った結果として事故が発生した場合、会社に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
損害賠償請求をする方法としては、ご自身で会社と示談交渉も可能ですが、
・ 弁護士を通じて示談交渉を行う
・ 裁判を通じて損害賠償を請求する
といった方法もあります。
まとめ
運送業における労災事故は決して他人事ではなく、多くの方が危険と隣り合わせで働いています。
万が一、業務中にケガをしてしまった場合は、
1.すぐに会社へ報告する
2.労災保険の申請を行う
3.会社の安全管理に問題があった場合、損害賠償請求を検討する
この流れをしっかりと理解し、ご自身の権利を守ることが大切です。
労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
弁護士にご依頼いただくことで、過去の裁判例や文献を調査し、これまでの経験を踏まえて、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士は具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労働災害に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。
労災事故に関するご相談は、専門の弁護士がサポートいたします。お気軽にご相談ください。