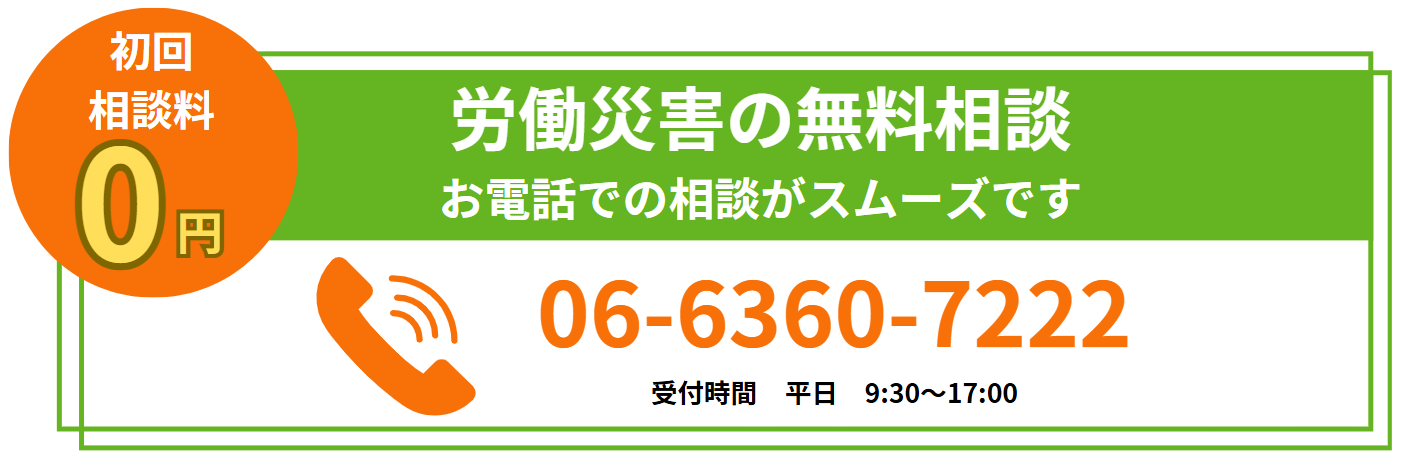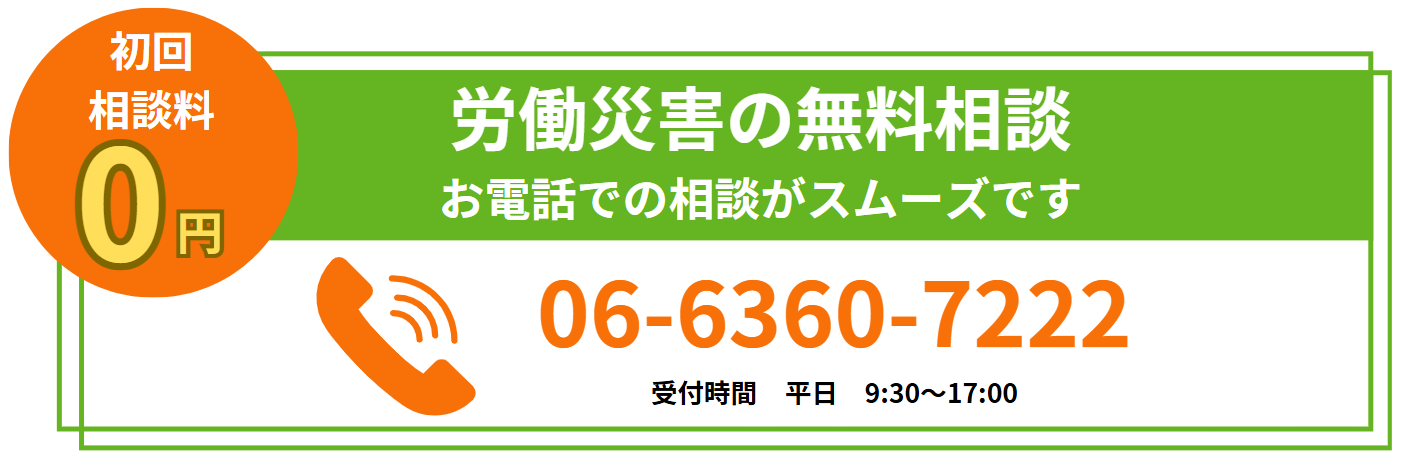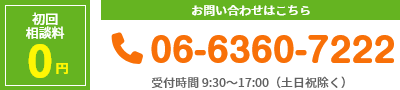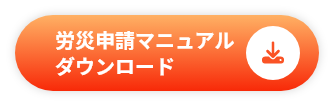精神疾患で労災保険の適用を受けている場合、まずは治療に専念することが大切です。この記事では、精神疾患における症状固定の考え方と、治療に専念すべき理由、そして弁護士への相談タイミングについて解説します。
治ゆ(症状固定)の考え方
一般論として治ゆ(症状固定)とは何か
労災において「治ゆ」(症状固定)とは、病気や怪我の症状が、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態を指します。
つまり、治療を続けても症状の改善が期待できず、その後の状態が安定していると考えられる状態です。
治ゆ(症状固定)となるとその後の手続きはどうなるのか
治ゆ(症状固定)と診断されると、治療は原則として終了し、労災保険による治療費の負担は終了となってしまいます(療養給付の打ち切り)。つまり、それ以降、病院で受診した場合、治療費は自己負担となります。
また、後遺症が残った場合は、治ゆ(症状固定)の診断を受けてから、障害等級の申請をして、その程度に応じて障害等級の認定を受けることになります。
障害等級が認定された場合
障害等級が認定されると、労災保険から等級に応じて障害(補償)等給付や障害特別支給金などが支給されます。
さらに、会社への損害賠償請求ができる場合は、障害等級が認められることによって、労災保険からは支給されない障害等級に応じた慰謝料や逸失利益(将来得られたであろう収入)を請求できることもあります。
いずれにしても、障害等級が認定されるかどうかは、労災保険からの支給額や会社に対する請求額が変わってきますので、今後の生活を保障する上で非常に重要です。
精神疾患における治ゆ(症状固定)
そもそも、どのような治療をするのか
精神疾患の治療は、患者さんの病状に合わせて様々な方法を組み合わせ、長期的な視点で行われます。
薬物療法やカウンセリングといった医学的な治療だけでなく、社会復帰を目指すリハビリテーションや、職場環境、家庭環境の調整など、様々な方法を組み合わせて、じっくりと時間をかけて症状の改善を目指すのが一般的です。
すぐには治りにくく、じっくりと治療した方が良い
精神疾患は、その性質上、医学的治療によって、すぐに治るものではありません。多くの場合、環境調整なども含め、症状の改善には時間がかかり、根気強い治療が必要です。焦らずに、医師の指示に従い、じっくりと治療に取り組むことが大切です。
その結果、後遺障害が残らずに、以前の生活に復帰できるのが一番です。
また、先ほどの説明のとおり、労災保険からの支給額や会社に対する請求額に関しては障害等級認定が重要なのですが、精神疾患の場合、治療期間中も症状が変動しやすく、どの時点で治ゆ(症状固定)といえるのか客観的な評価が難しいという側面があります。
そのため、弁護士としても、症状固定の判断や障害等級の見通しについての的確なアドバイスが難しいのが実際のところです。
ご相談いただくタイミングについて
精神疾患を抱え、治療をしながら生活することは、非常に大変なことです。
この記事でご説明してきました通り、症状固定や障害等級の認定は、ある程度治療が進んでから行われるものですし、精神疾患の症状は人それぞれですので、「症状固定時期はいつごろか」、「障害等級は認められるのか」といった判断は難しいものです。
焦らず、先のことを考えすぎずに、医師と相談しながら、ご自身のペースでじっくりと治療を進めていただき、最終的には、後遺障害が残らず、以前の生活へ復帰できることが一番かと考えます。
あまりに早期の段階で、精神疾患に基づく労災保険の障害等級申請や会社に対する損害賠償請求についてご相談いただいたとしても、弁護士もはっきりとした見通しをなかなか立てられない場合も多く、今後の見通しについて歯切れの悪いアドバイスしかできないことも多くあります。それによりさらに不安を増大させてしまっているかもしれません。
弁護士にご相談いただくタイミングとしては、十分に治療を続けたものの症状が残ってしまい、症状固定となり、障害等級の認定を受けた段階でご相談いただくのが、最もスムーズに進む可能性が高いといえます。
もちろん、労災保険の制度について教えてもらいたい、そろそろ症状固定と医師に言われているので今後の流れについて相談したいというような場合は、事案に沿ったアドバイスをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。