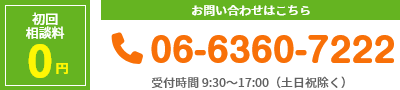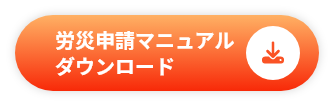はじめに
運送業は、私たちの生活や経済活動に不可欠な基幹産業です。しかしその一方で、業務中に労働災害に遭われる方が後を絶たない、事故と隣り合わせの業種でもあります。いわゆる交通事故のほかにも、トラックの荷台などからの「墜落・転落事故」は、時に命に関わる重大な結果を引き起こし、多くの運送業従事者やそのご家族を苦しめています。
この記事では、運送業における墜落・転落事故の実情と、被害に遭われた方が取りうる法的な救済手段、そして弁護士にご依頼いただくことのメリットについて、詳しくご説明します。
1.運送業における墜落・転落事故の実情
(「労働災害発生状況の分析等」より)
厚生労働省の統計によれば、運送業、特に陸上貨物運送事業は、製造業に次いで労働災害の発生率が高い業種となっています。
また、運送業においては、死亡者数に限れば「交通事故」が最も多いのですが、死傷者数でいいますと荷役作業中等の「墜落・転落」が最も多くなります。
「墜落・転落の事故が多いのは軽微な事故が多いのか?」というと、そういうわけではなく、一定の高さからの墜落・転落となるため、骨折や頭部損傷など、治療とリハビリに長期間を要する重篤な怪我をして、長期間の休業を余儀なくされるケースが多いのも特徴です。
2.運送業における墜落・転落事故の原因、実際の事故事例
運送業における墜落・転落事故が多発する背景としては、運送業特有の作業環境や、時に安全対策が不十分なまま作業が進められてしまう実態があります。次のような事故をご自身で経験したり、周りで聞いたことはないでしょうか。
①トラック荷台からの積み下ろし作業中の墜落・転落
平ボディのトラックの荷台(高さ約1.2メートル)で、シートを外す作業中にバランスを崩して地面に墜落し、頭部を強打して重傷を負った。当時は雨上がりで荷台が濡れており、滑りやすくなっていた。
②テールゲートリフター使用時の事故
テールゲートリフターで荷物を降ろす際、リフターの積載荷重を超える荷物を載せたため、リフターが傾き、荷物もろとも作業員が地面に転落して、足を骨折した。
③不適切な昇降方法による墜落
荷台から降りる際に、正規のステップを使わず、タイヤやバンパーに足をかけて飛び降りようとして足を滑らせ、アスファルトに手をついて手首を骨折した。
④高所での作業(荷崩れ防止のためのシート掛け、固縛作業など)における墜落
強風の中、トラックの荷台(高さ約1.5メートル)でシート掛け作業中、風にあおられたシートと共にバランスを崩して墜落し、腰椎を圧迫骨折する大怪我を負った。
これらの事故事例から見えてくるのは、
・作業環境の不備、
・安全装置の不使用、
・そして「これくらい大丈夫だろう」という油断や慣れ
が事故を引き起こす大きな要因となっていることです。
会社側には、このような事故が起こらないように、労働者が安全に作業できる環境を整備し、適切な指示・教育を行う義務があります。
もし、これらの事故に類似した状況で被災された場合、会社側の安全対策が不十分であった可能性もあります。自分だけの責任だと抱え込まずに、どのような救済方法があるのか、まずは専門家である弁護士にご相談ください。
3.労災申請をすることのメリット
他の記事で詳しく記載しているとおり、労災保険は、業務中の事故やケガに対して適用される公的な保険制度で、労働者が一定の補償を受けられるようになっています。
会社の規模や雇用形態に関係なく、正社員はもちろん、パートやアルバイトなどの非正規雇用の労働者にも適用されます。
主な補償内容は以下の通りです。
・療養補償給付(治療費の補償。病院での自己負担は原則不要)
・休業補償給付(労災による休業期間中の給与の約80%が支給される)
・障害補償給付(後遺障害が残った場合、その程度に応じた補償金が支給される)
・介護補償給付(後遺障害で介護が必要になった場合の補償)
・遺族補償給付(死亡時に遺族へ補償金が支給される)
・葬祭料(労災事故で亡くなった場合、葬儀費用が支給される)
もし労災事故に遭ったら、まずは労災保険に申請をして、保険金の支給を受けられるべきです。
「会社に迷惑がかかるのでは…」「手続きが面倒なのでは…」といったご心配から労災申請をためらう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、労災保険の利用は労働者の正当な権利であり、会社もこれに協力する義務があります。また、申請手続きが複雑で分かりにくいと感じる場合でも、私たち弁護士がサポートいたしますのでご安心ください。
4.会社に対する損害賠償請求について
労災保険からの給付は、治療費や休業中の所得の一部などを補償するものですが、精神的な苦痛に対する慰謝料や、後遺障害によって失われた将来の収入(逸失利益)の全額まではカバーされません。
これらの損害について会社から十分な賠償を受けるためには、会社に「安全配慮義務違反」があったことを主張し、立証する必要があります。
安全配慮義務とは?
会社(使用者)は、労働者が安全で健康に働くことができるように、必要な配慮をする義務を負っています(労働契約法第5条)。これを安全配慮義務といいます。
運送業における墜落・転落といった事故の危険性を予見し、それを防止するために具体的な措置を講じる義務が会社にはあります。
安全配慮義務違反が認められる場合の具体例
以下のような事情がある場合、運送業における墜落・転落事故でも会社の安全配慮義務違反が認められやすくなります。
①労働安全衛生法および関連規則の違反
・法律で設置が義務付けられているにもかかわらず、安全な昇降設備(踏み台、階段、テールゲートリフターなど)を設置していなかった、あるいは破損したまま放置していた。(例:最大積載量2トン以上のトラックに昇降設備がなかった)
・保護帽の着用が義務付けられる作業であるにもかかわらず、会社が着用を指示しなかった、あるいは着用していないことを知りながら黙認していた。
・高さ2メートル以上の場所での作業にもかかわらず、安全帯を用意していなかった、あるいは使用方法を教育していなかった。
・テールゲートリフターの操作に関する特別教育を実施していなかった、あるいは危険な使用方法を指示・黙認していた。
・過積載が常態化しており、それが荷崩れや不安定な作業環境につながった。
②危険な作業環境の放置
・荷台が滑りやすい状態(雨、雪、油、整理不良など)であることを認識しながら、清掃や滑り止め対策を指示しなかった。
・照明が不十分で暗い場所での作業を指示した。
・不安定な積み荷の上での作業を指示したり、黙認したりした。
③不適切な作業指示・管理体制の不備
・経験の浅い作業員に、十分な教育や訓練を行わずに危険な作業をさせた。
・無理な作業スケジュールを組み、作業員が焦って不安全な行動をとらざるを得ない状況を作り出した。
・「飛び乗り・飛び降り」などの危険な行為が常態化しているのを知りながら、具体的な改善措置を講じなかった。
これらの事情に心当たりがある場合は、会社に対して安全配慮義務違反を根拠とした損害賠償請求ができる可能性があります。
事故の状況を詳しくお伺いし、会社の責任を追及できるかどうか検討し説明いたします。
事故に関して、「何か腑に落ちないな」と感じる点があれば、まずはご相談ください。
5.弁護士に労災申請や会社への損害賠償請求を依頼することのメリット
事故に遭われた後、治療を続けながら、ご自身やご家族だけで全ての手続きや交渉を行うことには、多大な困難と精神的負担が伴います。
私たちにご依頼いただくことで、下記のようなメリットが得られます。
①労災申請の全面的なサポート
煩雑な手続きのご説明、お手伝いし、また、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する際のポイントをアドバイスしたり、必要な検査結果を収集したりするなど、適正な等級認定を得るためのサポートを行います。
②会社に対する損害賠償請求
安全配慮義務違反の的確な主張立証に必要な準備(証拠の収集・保全)や関連する法令や裁判例の分析を行い、会社との交渉・訴訟の準備を進めていきます。
また、様々な知識と経験が必要となる、具体的な損害賠償額の算定も行います。
③精神的な負担の軽減
事故によるお怪我の治療やリハビリだけでも大変な中で、不慣れな法的手続きや会社との交渉をご自身で行うことは、大きな精神的ストレスとなります。
「法的なことは専門家に任せている」という安心感が心のゆとりにつながります。
もし、あなたが業務中に墜落・転落事故に遭われたり、ご家族がそのような事故で苦しんでいらっしゃるなら、決して一人で抱え込まず、できるだけ早く私たち弁護士にご相談ください。私たちは、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。
ご相談は無料です。まずはお気軽にご連絡ください。