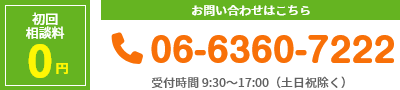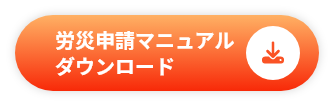はじめに
足指の骨折は日常生活でも起こりやすいため、「ただの足の指の骨折だから大したことない」と思われがちですが、実際には歩行や仕事への影響が大きく残るケースがあります。
この記事では、労働災害による足指の骨折について、「労災保険」での後遺障害等級の目安や、弁護士に相談するメリットについて詳しく解説します。
足指の骨折につながる労働災害の主なケース
足指の骨折は、「家具に足指をぶつけた」といった日常生活での事故に限らず、労働の現場においても多く発生しています。例えば、以下のようなケースが挙げられます。
・作業中にクレーンで吊り上げた荷物や、手で運んでいた重量物が足の上に落下した。
→特に、建設現場や製造業の工場、倉庫内での作業では、鉄骨や機械部品、積荷などが落下するリスクがあり、安全靴を履いていても足指の骨折に至るケースもあります。
・工場や倉庫、店舗などで使用される台車との接触や挟まれ
・製造業の工場などで、機械の点検や清掃作業中に、誤って機械が作動してしまい、回転部分や可動部に足指がはさまれたり、巻き込まれる事故
・脚立やはしご、足場など高所からの墜落・転落による受傷
足指の骨折の後遺障害等級の目安
労災保険における後遺障害等級は、骨折そのものではなく、骨折後に残った「機能障害」(動かしづらい)、「神経障害」(痛みや痺れが残る)の程度によって判断されます。
足指の骨折について、認定される可能性がある後遺障害等級は次の通りです。
機能障害に関する後遺障害等級
| 第7級の11 | 両足の足指すべての用を廃した場合 |
| 第9級の11 | 一方の足の足指すべての用を廃した場合 |
| 第11級の8 | 第1足指(親指)を含む、2本以上の足指の用を廃した場合 |
| 第12級の11 | 第1足指(親指)または他の4本の足指の用を廃した場合 |
| 第13級の10 | 第2足指(人差し指)の用を廃した場合、第2足指(人差し指)を含む2本/第3足指(中指)以下の3本の足指の用を廃した場合 |
| 第14級の8 | 第3足指(中指)以下の1本または2本の足指の用を廃した場合 |
「足指の用を廃した場合」とは
障害等級表において、以下のような状態が「足指の用を廃した場合」に該当します。
・第1足指(親指)の末節骨の長さの1/2以上を失った場合
・第1足指(親指)以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
・中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限される場合
骨折部分に痛みやしびれが残った場合(神経症状)
第12級13号(局部にがん固な神経症状を残すもの)
第14級9号(局部に神経症状を残すもの)
第12級と第14級の違い
第12級は、MRI画像やレントゲン画像などの客観的検査により、症状が医学的に証明できる場合が対象です。他方、第14級は、医学的証明はできないが、事故の状況や治療経過から症状の存在が医学的に説明可能な場合が対象とされます。
足指の骨折の後遺障害認定のポイント
後遺障害等級の認定においては、レントゲン画像や医師の後遺障害診断書が重要です。
痛み・痺れなどの神経症状の場合は、その内容を診断書にしっかり記載してもらうことが不可欠になります。痛みやしびれにより困っている具体的な症状・生活への影響(長時間歩けない・夜も痛みで眠れない等)を医師に伝えると、診断書に反映されやすくなります。
後遺障害等級が適切に認定されるかどうかで、障害補償給付の有無や給付額に大きな差が出る可能性があるため、後遺障害等級の手続きに不安がある場合は、このタイミングで弁護士に相談するのをおすすめいたします。
まずは「労災保険」の申請を
労災保険は、業務中のケガに対して適用される公的な補償制度で、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの非正規雇用者にも適用されます。
労災保険からは、療養補償給付(治療費の補償。病院での自己負担は原則不要)、休業した場合の休業補償給付などを受けることができますので、業務中に足指をケガした場合は、まずは労災保険を申請することをおすすめします。
また、骨折が治った後も後遺障害があれば、その程度(後遺障害等級)に応じて障害補償給付が支給されます。
損害賠償請求について
労災保険からの給付により一定の補償は受けられますが、通院や入院による慰謝料や、後遺障害によって失われた将来の収入(逸失利益)の全額まではカバーされていません。
ただし、労働災害について会社に使用者責任や安全配慮義務違反がある場合には、これらについて、会社に対して損害賠償請求が可能なケースもあります。
弁護士に相談するメリットとタイミング
事故直後から治療・通院・入院・リハビリが続くなかで、労災手続きや会社との交渉まで自力で行うのは大きな負担であると思われます。弁護士に相談・依頼いただくことには、次のようなメリットがあります。
適正な後遺障害等級の認定に向けた支援が受けられる
適切な後遺障害等級の認定を受けるには、医師が作成する後遺障害診断書の記載がとても重要です。弁護士に依頼された場合は、後遺障害診断書の作成を医師に依頼する際のポイントをアドバイスするなどの支援が受けられます。
損害賠償請求の検討
会社や加害者に対し損害賠償をすることをお考えの場合、証拠収集の上、会社や加害者の責任の有無を検討し、損害額の計算をすることが必要ですが、法律知識や経験がない方には難しい作業です。弁護士に依頼する一番のメリットはこの難しい作業を任せられる点にありますし、会社や加害者との示談・裁判も弁護士であれば任せることができます。
精神的な負担が軽くなる
弁護士から後遺障害等級の認定の支援を受け、損害賠償請求に向けての準備を専門家である弁護士に任せることで、ご本人はケガや病気の治療・リハビリに専念することができるようになります。ご本人だけでなく、ご家族の精神的な負担の軽減にもつながります。
「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を考えるお役に立てるかと存じます。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。